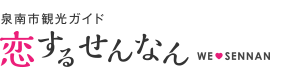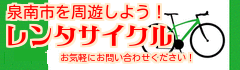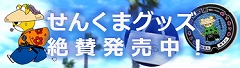泉南市内の御朱印がいただける神社・寺院をまとめました。
(google my map を挿入予定です)
各社寺の詳細については、下線付きの社寺名をクリックしてください。詳細な紹介ページに移動します。
海側
【浜街道周辺】
1.男神社
 初代天皇・神武天皇東遷ゆかりの市内随一の古社です。春にはヒメボタルの飛び交う深い緑の参道は、まるで古代へとタイムスリップしていくかのような神秘的な空間です。拝殿の前には、夫婦円満のご利益があるという「夫婦くす」、子どもの健康を守るという「ムクロジの木」(大阪府内最大級)といったご神木があります。
初代天皇・神武天皇東遷ゆかりの市内随一の古社です。春にはヒメボタルの飛び交う深い緑の参道は、まるで古代へとタイムスリップしていくかのような神秘的な空間です。拝殿の前には、夫婦円満のご利益があるという「夫婦くす」、子どもの健康を守るという「ムクロジの木」(大阪府内最大級)といったご神木があります。
男神社では、月ごとに季節感溢れる異なる御朱印がいただけます。拝殿に向かって左手にある社務所までお声がけください。
午前9時~午後5時の間に社務所まで。
2.光平寺
 光平寺は、発掘調査によって、その創建は平安時代後期まで遡ると考えられる寺院です。戦国時代は根来寺の末寺として広大な寺域を有していましたが、天正年間、信長・秀吉の紀州攻めの際焼失し、その後再建されたと伝わります。明治時代の神仏分離令までは男神社(おのじんじゃ)の神宮寺でもありました。緑の寺庭の奥に静かに佇む南北朝時代の五輪塔は泉南市の歴史を語る上で貴重な文化遺産です。
光平寺は、発掘調査によって、その創建は平安時代後期まで遡ると考えられる寺院です。戦国時代は根来寺の末寺として広大な寺域を有していましたが、天正年間、信長・秀吉の紀州攻めの際焼失し、その後再建されたと伝わります。明治時代の神仏分離令までは男神社(おのじんじゃ)の神宮寺でもありました。緑の寺庭の奥に静かに佇む南北朝時代の五輪塔は泉南市の歴史を語る上で貴重な文化遺産です。
毎月第1日曜日10時~16時に開寺されます。ご参拝・御朱印ご希望の場合は事前にお問合せください。
光平寺
3. 茅渟神社

社名にちなみ、チヌ(黒鯛)愛好家が供養と釣りの安全を祈願し全国から訪れる神社です。熊野詣が盛んになる平安時代、庶民が八王子権現を勧請したのが起源とされています。豊臣秀吉の根来攻めで一度焼失しました。現在の社はその後再建されたものです。チヌをモチーフにしたお守りやおみくじが人気です。
社務所までお声がけください。
茅渟神社
4. 南泉寺

樽井の地名発祥の寺です。名水が湧いたという「虚空蔵井戸」が本堂裏にあったとされます。信長の紀州攻めにより全焼する以前は、広大な寺領を有し、樽井台地に寺町を形成していました。※本堂は、現在修復工事中です(令和6年頃完了予定)
(修復工事中は、事前に電話連絡すれば、仮の御堂でご本尊にお参りでき、また、御財印・御朱印もいただけます。連絡先については、↓の備考欄をご覧ください)
5.里外神社

大坂の陣に赴く武将が残していったと伝わるえびすさまも祀られており、十日戎には、多くの参拝者でにぎわいます。十日の餅投げ神事も知られています。境内に残る王餘魚淵(かれいがぶち)には、熊野に向かう後鳥羽上皇に献上した「岡田ガレイ」が飼育されていたといわれています。
御朱印ご希望の方は社務所のピンポンを鳴らしてください。
【熊野街道周辺】
6.長慶寺

別名「あじさい寺」。毎年6月には、小高い丘にある境内のあちこちが紫陽花の花で彩られます。
御朱印は鳳凰堂のそばの寺務所を訪ねてください。
本堂から裏手の駐車場へ。一段下がった高台にあります。
7.真如寺

真如寺(法性山寂静院)は、正式な本陣である角谷家に対し、紀州藩の隠れ本陣として使われていました。
部屋の襖をはずすと500人もの一行が一堂に会することの出来る大広間としても使え、江戸時代には参勤交代の一行が利用しました。
また、門脇の樹齢300年の「かいづかいぶき」は松平主税(後の徳川吉宗)が植樹したと言われています。
8. 市場稲荷神社

熊野街道の近く、信達市場にある神社で、ご祭神の豊受姫大神は、農業をはじめとし、機織(はたおり)その他各産業の発展をつかさどる神様です。創建は天仁元年(1108年)、伊勢外宮より勧請されたと伝わります。江戸時代、この周辺に市(いち)がたつようになり賑わったため、「商売の神様」として祭られるようになり、「市場稲荷神社」と呼ばれるようになりました。
御朱印ご希望の方は、社務所の玄関のピンポンを押してください。
9. 往生院

熊野街道沿いにあり、679年に天武天皇の勅願寺として創建されたと伝わります。中世以前は七堂伽藍を有する大寺院でしたが、豊臣秀吉の根来寺攻めの兵火によって、堂塔すべてを焼失しました。
創建者である道昭は、遣唐使のひとりとして留学した際、「西遊記」に登場する「三蔵法師」のモデルである唐の僧侶玄奘三蔵の教えを受けたことや、行基の師としても知られる名僧です。
山手
【信達金熊寺地区】
10. 金熊寺

金熊寺は、別名「一乗山観音院」と云い、真言宗仁和寺の末寺です。
白鳳十(681)年、修験道の開祖とされる役行者が創建したと伝わります。2024年6月、日本遺産「葛城修験ー里人とともに守り伝える修験道はじまりの地」の構成文化財として追加認定されました。
毎月22日は、本尊如意輪観音の御縁日であり、如意輪観音がデザインされたこの日限定の御朱印が授与されます。
11. 信達神社

古くは金熊寺大権現宮と称し、金熊寺の鎮守社でした。明治の神仏分離政策により、金熊寺から分離独立し、信達神社となりました。江戸時代にこの地の豪族矢野氏が奔走し、五間社流造(桁行5間梁行2間)の立派な本殿を建てたと伝わります。江戸時代前期の建築では、大阪府最古級のものと考えられています。
鳥居とは反対側に社務所があります。御朱印は社務所をおたずねください。
信達神社
【新家】
12. 種河神社

緑に囲まれた長い参道と4月には桜が美しい神社です。
2月の湯神楽神事、7月の祇園祭にもたくさんの参拝者が訪れます。
御朱印については、茅渟神社で、種河神社におまいりしてきたとお伝えしていただいてください。