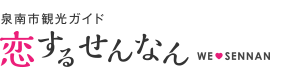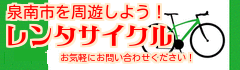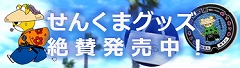-
古代寺院跡の桜
国の史跡である白鳳時代の古代寺院「海会寺(かいえじ)」跡には、建設に携わった豪族の屋敷跡を見ることができる広場や散策路があります。ここは、春になると広場一面が桜の花で覆われます。また、回廊跡では、一部復元された柱廊、五重塔基壇を背景に枝垂れ桜が優雅な姿をみせます。
-
モダンな日本庭園に咲き誇るツツジとサツキ
林昌寺 (Rinsho-ji Temple) のツツジ・サツキ
林昌寺(りんしょうじ) (Rinsho-ji Temple) の山号は「躑躅山」といい、平安時代後期、堀河天皇が行幸のおり、山躑躅(つつじ)が見事であったことから、山号を躑躅山と改めたという歴史があります。京都・東福寺「本坊庭園」等で知られる日本を代表する作庭家 (landscape architect)・重森三玲(しげもりみれい -SHIGEMORI Mirei)作のモダンな寺庭では、毎年4月下旬から、庭の上部と向かって左側の刈込にツツジが咲き乱れ、5月中旬から下旬にかけて、中央の波のような大刈込のサツキが見頃を迎えます。昔、躑躅丘と言われた丘陵の一角であり、山の斜面を利用した見事な景観です。
-
愛された4万房の藤
古い街並みが残る熊野街道にある梶本さんのお宅では、樹齢40年を超える1本の野田藤が毎年4万もの花房をつけます。4月中旬から下旬の藤の見頃には、一週間程度「熊野街道信達宿のふじまつり」が開催され、藤棚が一般公開されるため、遠方からの花見客で賑わいます。期間中は、藤棚のそばに観賞台が設置され、藤を上から観賞することができます。眼下に広がる藤の花は、まるで紫の雲海のようで圧巻です。(ふじまつり・一般公開の予定については、↓↓の備考欄をご覧ください)
花スポット | 恋するせんなん
- 恋するせんなんTOP
- 花スポット